|
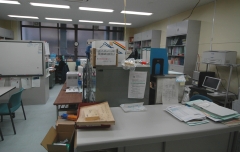
|
|
安全衛生管理室内
|
土)安全管理は管理室が全てやると誤解されがちですが、基本的には現場の責任者、つまり研究の責任を持つ者が安全管理を主導することになります。例えば、研究でこういう危険な物質を扱います、こういう装置を使います、そういうことを決める方が研究の安全を確保する責任があるわけです。会社では、上から工場長、部長、課長、グループ長、研究者というように指揮命令系統も責任体制も決まっています。人の命にかかわることですから、非常に厳格におこなわれています。大学ではそれほど組織が明確ではありませんが、研究科長、専攻長、研究室の責任者、スタッフ、それから学生という組織になっています。指揮命令系統とまではいえないのかも知れませんが、この組織で責任を持つことになっています。
|